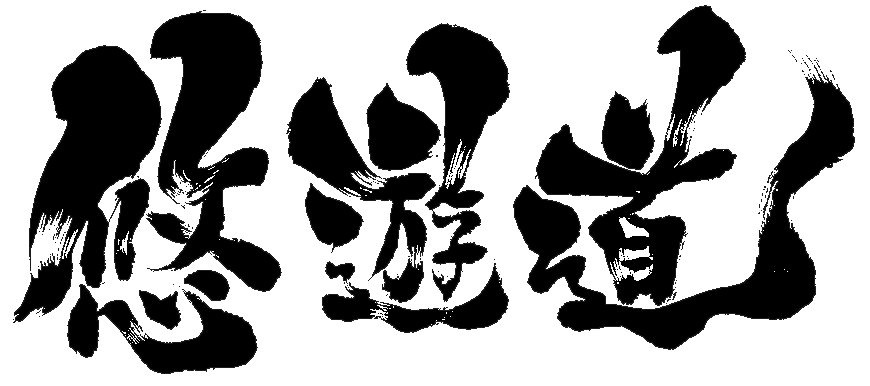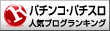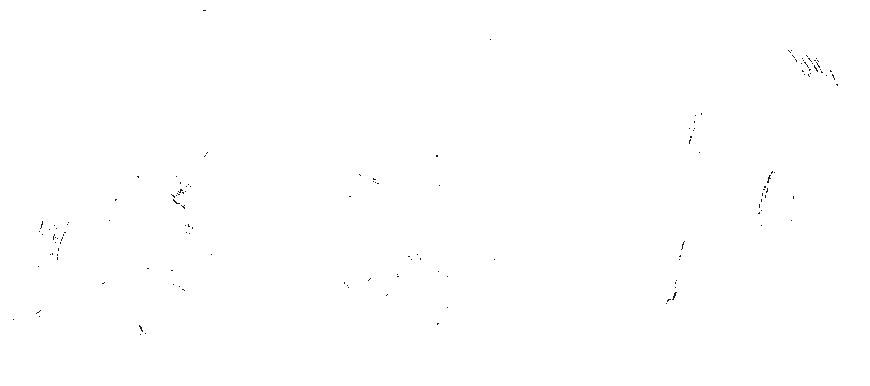ぱちんこ閑話休題
懐古主義「地域の社交場」
はい皆様ご機嫌麗しゅうっ!全国的にもう暑さがヤバイですね…。ここ最近は毎年「史上最高の暑さ」を繰り返してますが、こちら東北宮城でも、ほとんど雪が降らなかったここ数年を考えると…1年通して気温が上がっちゃってる感じなんですかね。そのうち40℃が普通になるような事態になったら、それこそパチンコ屋が「地域の社交場」としての地位を取り戻せるキッカケになれないかなぁ…なんて考えてながら過ごしております。
さてさて、今回はそんな「地域の社交場」としてパチンコ屋が機能していた古き良き時代と、今じゃどう違ってしまったの?って話をさせてもらう事にしましょうか。
小銭でも打てたパチンコ
打ち手として一番感じる違いは、まず金をかかり方かな。昔は1円パチンコなんて無く、全台4円(スロットは20円)で営業していたのにも関わらず…なぜ昔の方が門戸が広かったのか。当時はアレパチや権利モノを筆頭に機械的に荒いヤツもあったが、羽根モノ等の「勝っても負けても1万円まで」のような機種も、ちゃんと立ち位置を確保していたのが大きい。金持ってる大人はアレパチで「ぴゅい♪」に酔いしれると同時に、当時高◯生だったナカムラは、、
( ゚Д゚)「今日は3800円も持ってるぜ!」
くらいのノリでも、十分打ちに行けた。地味だがこの800円の部分…小銭でも打てたのはかなり大きいと思うんだ。今では1000円未満は完全に門前払いで、玉を借りるスタートにも立てないのが現実だもんね。その分、やられた時はケツの毛まで抜かれて財布の中身が100円未満になり、帰りにジュースも買えないという大惨事にもなるんだけどもww
等価前提
小銭で打てなくなったとは言え、今でも羽根モノは存在してるじゃん!って意見もあるだろうが、違うのよ。昔はホール全体の1/4くらいが羽根モノだったりで、今みたいに「申し訳程度」の設置じゃないから、主力として機能してたのよ。そこが大きな違い。
そもそもなぜ今は羽根モノのような機種が稼働しないのかと言うと、根本的に等価営業(準等価含む)にフィットしないから。もうね、これはどうしようもない。40玉で4000個打ち止めだからこそ、小銭でもワンチャンあった。ほぼ等価で持ち玉無制限になった今では、店も羽根モノは扱いづらい上に儲からない、だから気まぐれでしか導入しない。打ち手もそれでは面白みが無い…だから双方に需要が無いのだ。
出率100%を超えるギャンブルは世界でパチンコだけだった
海外カジノでも競馬でも競輪でも何でも、出率100%を超えるギャンブルなんてものは無いが、当時のパチンコは客が100玉借りて打って160玉にしてチャラ…これこそパチンコが「大衆娯楽」として世に根付いた核心である。
割数で言うと16割分岐。だから店は玉を出せる。出せるから客は遊べるのだ。
当時の還元の割り振りを例えてみると…
1回100円でサイコロを振らせ、出た目に応じて賞金とする。
①200円当たり
②150円当たり
③100円当たり
④50円当たり
⑤ハズレ
⑥ハズレ
これで売上600円の500円還元だ。還元率は同じとして考えても、今は機械のスペックと等価営業の相乗効果で…
①500円当たり
②ハズレ
③ハズレ
④ハズレ
⑤ハズレ
⑥ハズレ
みたいな、ちょっと極端かもしれないがこんな感じ。
一撃の大きさは断然今の方が魅力的ではあるが、他に救いがなさ過ぎるのよね。だから繰り返し遊ぶって事が異常に難しい。つまり一般層のライフワークにはなり得ない。物好きの単発遊びか富裕層のみの娯楽だね。
つづく