文庫本の原稿を書かせてもらうことになったA氏だが、なんせ原稿料が発生する文章など、当然一度も書いたことがないわけで、一体どのように書けばいいのか、最初はそれなりに悩んだようだ。既に掲載されている記事を参考に原稿を書く、言うは易くだが行うは難し、それでもここで認められないと好きな雑誌で原稿を書くという目標が途絶えてしまう。果たしてどうなることやら……。
―いよいよ原稿を書くところまで来たわけですね。ただ、最初の内は色々と戸惑ったようですが。
「文庫本はそれまで本誌で紹介されていた多くの機種ページを再構成、つまり機種に特化したガイドブックのようなものですが、それで本誌の内容をそのまま書き写すというわけには当然いきません。編集部ではリライトという言葉が使われていましたが、ようするに上手にまとめて書けばいいよと、そんな感じでした。例えば500字程度で書かれていたものを300字くらいにまとめる、その機種の特徴や読者に伝えたいことはきちんと書く、後は分かりやすく、正しい日本語で書くと、そのように指導されました」
―なかなか難しいですね。
「正直、パチンコ雑誌で細かく色々と言われるとはあまり思っていませんでした。笑いを取るような文章、面白おかしく書ければいいのではと思っていたのですが、決してそうではなかった。まずはきちんとした日本語で書くこと、それを良く言われましたね。受けを狙った文章はその後でいいと」
―なるほど。
「ただ、いざ書き始めてもなかなか進まなかったですねー。と言うのも時は92年、ワープロ普及期に当たると言えばそうなのですが、特に仕事に使うのでなければ個人的に所有している人はそれほど多くなかったと思います。自分は一応持ってはいたのですが、それはパチンコやパチスロの収支をきちんとつけておこう程度の気持ちで買っておいたもので、本格的に文章を書くために使っていたわけではなかった。だから、キーボードを打つ速度も大したことはないわけで、ハタから見ていたら手書きと変わらないじゃないかと言われたでしょうね。ですから、いざ書く時は所定の原稿用紙に鉛筆で手書きでした」

―手書きですか。
「はい。文字量が決まっていて、例えば縦書きの文字数が16字で行数が20行なら最大320字となるわけです。実際には改行が入ったりしますから、それよりは少なくなります。実際、書いていて困ったのは指定の文字量をオーバーしてしまうことが多く、なかなかうまくまとめられないんですね。でも、新人の分際でもう少し文字量を増やしてほほしいとか、なかなか言えませんよね。おまけに手書きですから、書き直す度に何度も何度も消しゴム使ったり、棒線引っ張って訂正したり、文章を書く労力と言うより、手や指を使う労力の方が大変でした (笑)」
―それでも何とかやり切ったと。
「そこで根を上げるわけにはいかないわけで、何とか原稿のマス目を埋めたと、そんな感じでしたね。何度も赤を入れられましたが、まあボロクソ言われるようなことはありませんでした (笑)。ただ、原稿を書くということは大変なことなんだと、特にきちんとした日本語で分かりやすく書くというのがいかに大変なことか、それは身に染みて感じましたね。当時の編集長N氏や副編集長だったM氏に良く言われたのが、難しいことを難しく書くのは誰にでもできること、難しいことを簡単に分かりやすく書くことが大切だと、それは今でもそう思いますね」
―なかなか重みのある言葉ですね。
「それは今のG誌にも受け継がれていると思います。別段、身びいきするわけではありませんが、ライバル誌が休刊する中、何とか生き残っていられるのも、雑誌として文章を蔑ろにしていないからでしょう。確かに昨今は文章云々よりも誌面を彩る女性ライターや映像を収録したDVDがメインになっている感はありますが、それでも本を開いてみて全く ‘文章’ が掲載されていないということはないですよね。機種紹介にしても、我らの安田氏のコラムにしろ、文章はしっかりしたものです。編集者がきちんとチェックし、場合によっては何度も書き直してもらったり、そんな中で時には編集とライターの間で意見の相違等が出てくることもあるのですが、それでもお互いいいものを作るという感覚は持ち合わせていますから、結果的にはいいページが出来上がったりします。時にはメーカーやホールの思惑が入ってくることもありましたが、まあ、あからさまな圧力だったり、提灯記事だったり、僕が知る限り、そういったことはほぼほぼなかったと思います」
―昔はメーカーやホールさんとはあまり仲が良くなかったと聞いていますが……。
「元々、パチンコ業界って閉鎖的であまり表に出てこないんですよね。だから広報とか、メーカーによってはそういった部署がきちんと機能してなかったり、メディアに対する対応ができてなかったり、そのような傾向は確かにありましたね。だから、カタログひとつもらうのも一苦労でした。上野に行けばメーカーのショールームが幾つもありますが、今でこそ事前にきちんと連絡し、何日の何時に伺いたいのでどうでしょうか、それではよろしくお願いしますと言っておけば大体大丈夫でしょう。ですが、90年代なんて、身元を明かさず、いきなりショールームに行くことが良くありました。実際にあるホールの名前を使い、カタログをもらうんですね」
―どういうことです?
「例えば、神奈川のAホールの者ですが、今度出る新機種のカタログを一部くださいと、そんな風にショールームのスタッフに話しかけるわけです」
―ははは。
「それで大抵はうまくいきましたね。名刺を求められても、今切らしていますと言えばいいですし。メーカーショールームからしても、こちらを実在するホールの関係者としか思っていないですし、自社の台が売れればそれはそれでいいことですから、よろしくお願いしますとなるわけです。ただ、僕の経験ではないのですが、これはマズイという展開になり、即座にショールームから退店した話を聞いたことがあります」
―G誌の人間だとバレだと?
「いつものように神奈川のAホールですが云々という話をしたそうですが、すると、おかしいな、Aホールさんはさっきお見えになって試打もされていきましたよと言われ、あぁそうですか、そうですかと笑いながらそそくさとショールームを出たそうです」
―直前に本当のホール関係者が来ていたんですね (笑)。
「昔はそんなこんな、カタログもそうですし、新台の写真一枚撮るのも大変でした。その意味では、今は本当にいい時代になったものと思います。次回は文庫の原稿書きを経て、本誌で書くようになった頃を中心に話していければと考えています」
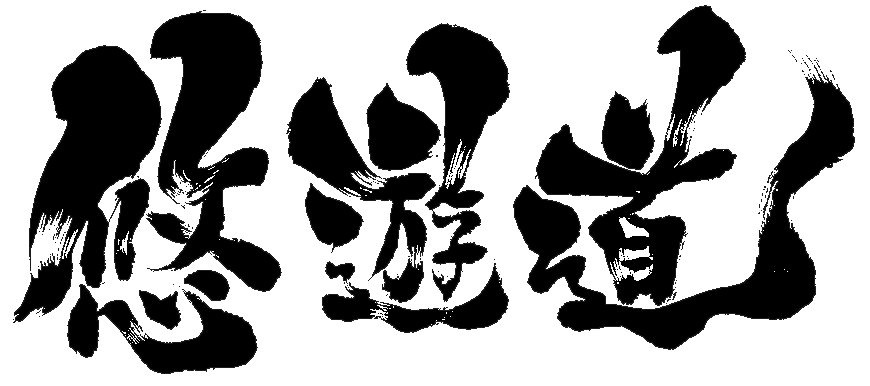


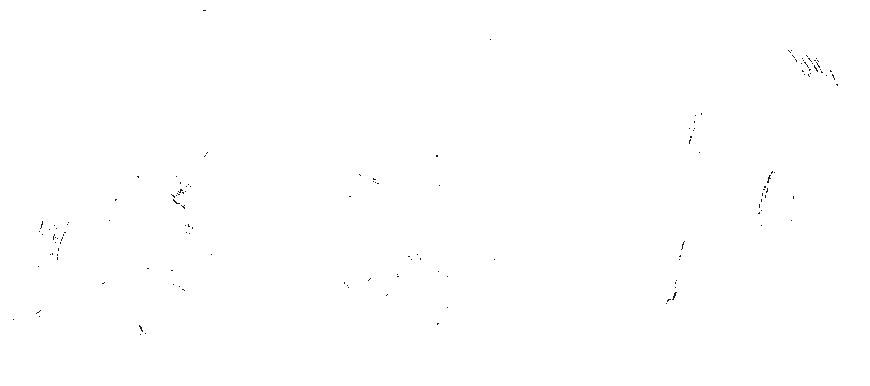
今なら普通に事件って言われそうな他人のふりですね~
昔はホールで写真撮るのもメモ取るのも大変だったってよく聞きますものね。
>>白いシローさん
ホール撮影とか(ドル箱山積みのシマとか)、当時はほとんどゲリラ撮りでしたね。冬場は服の下にカメラを隠したり、色々と工夫をしていました。メモは、うるさい店は確かにうるさかったですね。他のお客さんに迷惑になるからとか、ほとんど言いがかりとしか思えないことを言われたりして、それでも言うことを聞かなければ出禁ですからね。今のパチンコそのものが面白いかどうかは別として、今は本当にいい時代になったものです。