10年前までは地元のどのパチンコ店へ行っても勝てる自信があったし、実際に勝っていた。
一つのお店ばかり行くと目立ってしまうので、これを嫌う俺は複数のお店をローテーションしていた。
中でも、看板機種大海物語を甘く使ってくれていた老舗のD店では良い台を打てていて、高日当を得ていた。
「わしが止めたあの台、その後女が座ってすぐ当たって10連チャンしとる。いつも当たるのは女ばっかり、絶対この店なんかやっとる」
「そうやそうや、わしもそうや、もうこんな店来るか」
高齢者中心の客層、開店前から南側正面入り口の前は、文句を言いいつつもまた来る常連らのオカルト飛び交う井戸端会議の場となっていた。
それが今ではご多分に洩れず、わが町も外部資本の大手チェーン侵入と共にお客を奪われ、昔ながらの老舗店は閑古鳥店に落ちぶれていた。
開け閉めのメリハリがあったD店だったが、お客離れが顕著になると2度と開かなくなり、締めっぱなしの万年釘となるのに時間はかからなかった。
昔からお世話になったお店が、締める、飛ぶ、の負のスパイラルにて落ちていく様子に黙っていられなかった東雲(しののめ)明。俺だったらこうするという意見書を店長あてに出したこともあった。しかし、それが採用されることはなかった。
4度目の投稿も結局意味がなかったと感じ始めていた頃、ふと思った。投稿を一瞥した店長「そんなことは分かっている。しかし堅物のオーナーが認めないから無理」あるいは「お客風情が店の経営に口出しなどするな」か。
D店のオーナーがワンマンで鳴らしているのは耳にしたことがある。所詮雇われ店長、ということか。
生産性の無い職業パチンコに閉塞を感じ、多少経営に興味があった東雲。その後D店の面接に行くのに時間はかからなかった。
面接では「ゆくゆくは店長を希望」と主張。また、投稿をしたその意図も話した。投稿依頼非採用の理由はだいたい予想した通りだった。ただ、こういう投稿は初めてだったので強く印象に残ったとのことだった。そしてそれから僅か2年、晴れてパーラーでるでる店の店長になったのである。
店長になって分かったこと。新台の導入決定権はオーナーが握っている。目指すのは売上でなく、利益。前年比100%は絶対。
客数減、さらには4パチ客減により、売上以上に利益が取りにくい現状、4パチの釘を締めるしかない。前店長のボヤきも分からんでもない。しかし、ボヤくだけではやはり雇われ店長だな、とも思った。
地域1番店にのし上がった外部資本チェーンのS店など、地域のお店全ての釘の傾向などはパチプロ時代から分かっている。頭取りなど無駄なことはすぐに止めさせた。パチとスロの設置比率、島構成、換金率、など理想とする腹案はあったが、まず釘に手を付けた。
S店のヘソ釘に対し、沖海など主力機種について0.5ミリ開けた。S店は12.5ミリだったから13.0ミリにしたわけで、これは見た目でもハッキリ開いていると分かるレベルだった。
その代わり、やや下げ、ワープ、寄り、スルー、アタッカー釘を少しづつ締め、右側も締めた。しかし、釘を叩くという行為は簡単ではなかった。
ヘソ釘は右が下がってしまう。左手の添え方を変えるなど練習しても難しく、ペンチを使うこともあった。
釘を外から叩けても、内から叩くのも難しく、ややもすると釘の頭が傷だらけになってしまうこともあった。おかげで毎晩朝方までかかってしまった。
ハッキリとヘソ釘を開ける、しかしお客は直ぐに反応したわけではなかった。まず、ヘソを見て判断するいわゆるヘソプロが反応した。
沖海、北斗無双の島にヘソプロが増え、出玉感が出てくると、つられて一般客も少しずつ増えてきた。
最初は負けていた。しかし師匠と呼べる先輩パチンカーやパチンコ誌から勝ち方を学び、ボーダー論者になった薄っぺらなヘソプロ連中を手玉に取る自信はあった。
一般客が付くまでは泳がせた。付いてからも、まだヘソは締めない。打ち始めは回る。そして持ち玉になる。やがて回らなくなる。何故だが分からず首をかしげる。そんな調整を目指した。
売り上げは上がった。ただ、利益はトントン。これは持ち玉で粘るヘソプロが未だ多いからであったが、売上が150%になるまでは、と思っていた。
ヘソプロを追い出すのは簡単。ヘソを締めればいいだけ。ただ、それで一般客まで離れたら本末転倒。ゆえにそのさじ加減を考えていた。
そんなある日の朝、釘を1台1台吟味するお客がいるのに気付いた。痩せていて帽子を被り、地味な服装の初めてみる男だった。ありきたりだが、痩せ帽子(Y)と名付けた。
Yは沖海の島内の寄り釘の1番良い台を選んだ。そして殆ど席を立つことなく、無表情のまま閉店30分前まで打ちきった。終日の回転数も回転率も店1番。大当たり中の振り打ちなども器用にこなす様子を見ていて、パチプロ時代の血が騒いだ。
Yの打った台と、寄りのいいもう1台の沖海の道釘を少し上げた。翌朝、東雲は碁盤の目のように並んだモニターの前に座っていた。
Yは朝の並びの後方から入店し、前日の台をキープし釘を見たあと、他の台の吟味に入っていった。やがて戻ってきて打ち出す?いや、まだ打たない。再度釘を見ている。まさか変えた道釘に気づいたか?
ようやく打ち出すも、千円でヤメ、寄りのいいもう1台へ移動する。これも直ぐに打たず、釘を見ている。そして、結局打たずに席を立つ。
それを見ていた東雲「ほぉ」と思わず声を上げた。
「こいつ、やはり只者ではない。俺がプロ時代にもこの地域にこれだけのヤツはいなかった」
さて、バラエティ島へ移動したYはその中の1台に座った。
それを見ていた東雲は呟いた。
「まさか!?」
…………
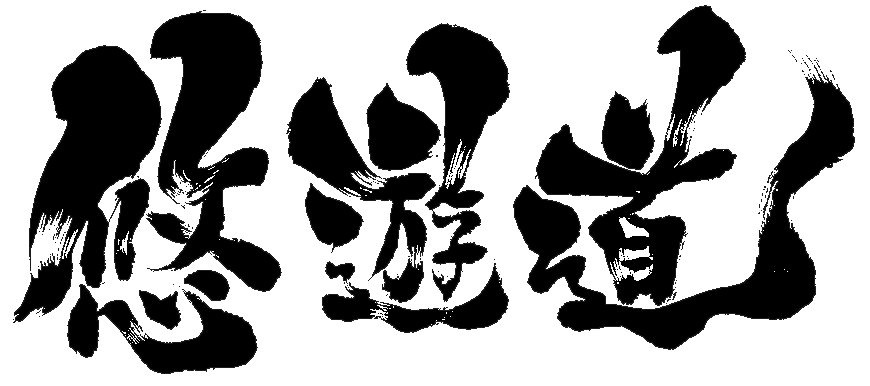


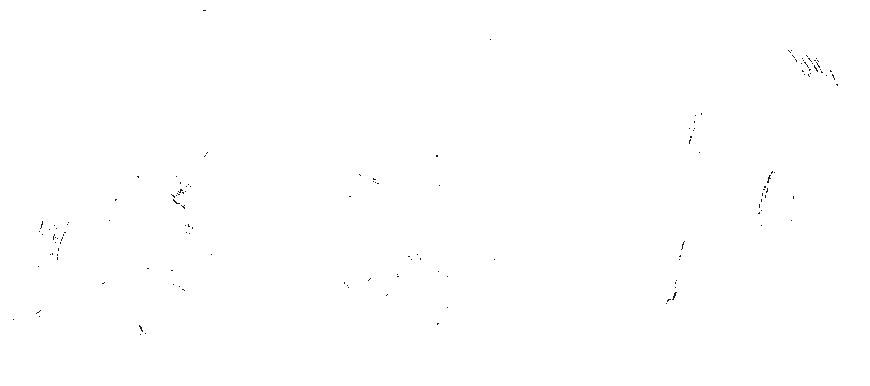
釘氏ゆきちさんを思い起こすような内容で読み入っちゃいました♪
>パチンコショートショート
>「まさか!?」
>…………
って続くんか~ぃ凸( ̄^ ̄) (笑)
パチドランカーKさん、コメントありがとうございました。
終わり方については、映画でもたまにある手法を取り入れました。
また、映画でも支持得られない作品は消えてしまうのと同様、続くかどうかは未定でございます。
面白いです。
続きをお願いします。
夜眠れません。
2円プロさん、コメントありがとうございました。
このショートショートの制作は3か月ほど要しましたので、簡単ではないですが、次作を考えてみます。
しののめ
知らない、いや、無知か!気になりました
東雲しらべました。
スンナリ決めたのかな?
3ヶ月ですか。まぁ既に三回いや4回めか珍しく読み返してるものづきもいるのでつまらんボツコメントもってそうはいかんか
ハマりました
匿名さん、コメントありがとうございました。
東雲と書いてしののめと呼ぶ・・・見た目、発音とも好きなので、いろんな候補の中から今回の主人公の名に採用しました。