もはや学生時代の話なんて、霞の向こうにある不明瞭な幻影みたいになってる。細部がぼやけて輪郭しか分からないながら、断片的に覚えている信頼度不明のパーツと歴史的事実を照らし合わせて考えるに、どうやらそれは1997年のことらしい。
当時俺は九州の片田舎で暮らしていた。
あの頃は共通の趣味をもつグループでいつも行動していたものだった。共通の趣味。これはセガが1993年に発売したアーケードゲームである「バーチャファイター」という格闘ゲームの事だ。当時はセガサターンという家庭用ゲームにも移植されており自宅でも手軽に遊べるようになっていて、我々5人は金曜の夜になると誰かしらの家に集まり、酒を飲んだりタバコを吸ったりしながら、夜通しそれでもって1マッチ50円を賭けて遊んでいた。
誰の家に集まるかはその時その時で違ったけど、とりあえずみんな当たり前にサターンを購入してたしアーケードスティックも完備してたので、例えば俺の家の事もあったし、そこからほど近いところにあるNの家の場合もあった。最も頻度が高かったのはうちからちょっとだけ離れたKという友達の家だった。
NもKも小学校の頃からの同級生で、当時は取り立てて仲が良かったわけじゃないけど、中学時分に急接近し、バーチャファイターを通じて高校入学前後に親友になった感じだった。それと中学から一緒になった連中と、あとは高校で邂逅した連中。色々いたけど出会ってからの歴の長さで言うとNとKは別格で、俺も当時は、まあ何となくコイツらとは一生連るんでいくんだろうなと、ぼんやり予感していたもんである。
さて。
夏目漱石の「こころ」という作品がある。友人である「K」を中心とした、恋愛トラブルと自殺に纏わる話だ。クリスマスとお正月を控えた2学期末のある日、当時やや文学にかぶれつつあった筆者は薄暗い部屋のベッドに横たわりながら、オレンジ色の常夜灯にて活字を追いつつ、なんだかいたたまれない気分になってしまった。ああ、漱石が時空を越え、俺を叱責している。開いたままのページを顔面に乗せて、大きく深呼吸する。古い本の匂いがした。
というのも、当時筆者は彼女が出来たばかりで、その彼女が元々Kと仲が良かった──というか、はっきりと付き合う手前の状態であった子であった。彼女とは一回K抜きのグループでカラオケに行った時に何となく仲良くなり、気づいたら二人で会うことになって、いつの間にそういう関係になってしまっていた。当然そのことは周りに言ってないしダマである。なんせKが彼女にお熱なのは誰が見たって明らかだったし、釘も刺されていたからだ。俺だって別に最初はそんなつもりは無かったのだけど、自然とそうなってしまったんだから仕方ない。要するにはその時点で、俺は彼女のことが大好きになっていたのだ。手放すつもりはもうなかったし、かといってKに謝るのも筋が違う。なんせ彼らはまだそういう関係になっていなかったのだから。
もう一度「こころ」の表紙に目を向ける。──状況まで似てやがるし、なんだってイニシャルまで同じなんだ。バツが悪い気分で本を閉じ、目を閉じて今後の計画を練った。角が立たず、悪者にもならず。彼女のことも守りつつ──。
結果、田舎の高校生が必死に考えた作戦は「俺のほうがKより先に彼女を好きだったんだもん」という反駁不能の強弁で通すという、子供みたいな詭策であった。
当たり前なんだけどそんなモンが通じるわけもなく。俺はそのバーチャグループの中で、何となくシカトされるようになってしまった。そりゃそうだ。誰だって心情的にはKの味方をするだろう。そう冷静に分析しつつ、俺の心はむしろ晴れやかだった。友達を喪失した悲しみより、大手を振って彼女とイチャコラできるという方が、性欲を持て余した男子高校生にとっては20京倍くらい重要であったのである。彼女は当時の俺よりも5つ上。22歳のOLであった。車もありお金もある。しかも年上の包容力と手練手管まで完備。俺がふにゃふにゃの骨抜きにされるのには3日もかからなかったと思う。俺はずっと女性に依存して生きていく事に最上の価値を置き「人生の勝ち組」と定義してるけど、そのヒモ根性みたいなのはこの時期に醸成されていると思われる。
また同時期に、彼女の友達連中……必然的に俺よりも年上の人々と仲良くなったのもデカかった。高校時代は何を学ぶかより、どんな人々と接するかのほうが遥かに重要である。その年頃の連中は年下の、ダチのダチみたいなのにすこぶる甘い。いいとこ見せたくて仕方ないのである。従って俺もそのグループの中でチョコレート煮込みの如くグデングデンに甘やかされ、ありていに申さばこの世の春みたいな状況になった。ちょっとアレににてる。スタンリー・キューブリックの「時計じかけのオレンジ」で、人権派の左翼に持ち上げられたアレックス君がベッドに寝っ転がったまんまフルーツ食べさせて貰うシーン。あれが当時の俺だ。
──だので、むさ苦しい部屋に集まって50円賭けて夜通しバーチャするのが、途端に5歳児の砂遊びみたいに思えて、結局、彼らとはその後ほとんど交流を持つことが無くなってしまった。
1997年の元旦。ノストラダムスの襲来予定日まであの2年を切った、滅亡秒読みムードのプレ・プレ・プレ・ミレニアムである。彼女が駆る車の助手席でふんぞり返りながら、早速ドライブにでかけた。普段は彼女がデート代等も全部出してたのだけど、その日ばかりはいつもと違う。なんせ俺の懐中にはシュート・ボール……つまり「お年玉」があるのだ。メシ代もホテル代も全部出すぜ……? くらいの気持ちだったけど、どういう訳だか俺が向かったのは「パチンコホール」であった。
彼女の友達連中が「パチンコが面白い」と盛んに言ってたのを思い出したからである。とはいえ当時の俺はガチでパチンコを遊ぶつもりなんかなく。要するにお金もあるし車もあるんだから、ちょっと背伸びしたくて「運試し」のつもりで提案したのだ。
「えー、パチンコ……」
「うん。ちょっと行かない?」
「いいけど……」
やや難色を示しハンドルを握る彼女。その太ももを助手席から揉みしだきながら何となく知ってるパチ屋までの道筋を案内する。到着したのはCという地元感丸出しの中小ホールで、今だったら100%入らない自信がある感じのお店だったんだけども、当時はそんなん知らないから普通に入った。そして入って3秒くらいで後悔した。 入り口からほど近い場所ある台のところに、見覚えのある連中がズラッと座ってる。そう、元・親友たちだ。
「うお……。ちょっと待った。帰ろう」
「え……?」
「アイツらいるんだよ」
「あー……。挨拶しないでいいの?」
首を振って手を引き、店を出た。彼女はKと俺とのいざこざは知らない。だってKは彼女にアタックすらしてなかったんだから。そういう意味でもやっぱり俺は悪くねぇのだけど、人にはそれぞれの角度から見たの主観的事実があって、さらにモラルの基準には高低差がある。俺が悪くないのは俺の角度と俺の高低で見てるからに過ぎない。多分彼らの中では俺は悪者だろうし、最悪なことに、俺は俺でその立ち位置に満足しつつ、この世の春を謳歌していた。いつの世も、そしてどのレイヤーも、既得権益者にはルサンチマンが集まるものなのである。そういうルールを肌感覚で知ってる就職超氷河期時代のシニカルな高校生だった俺は、「別の店に行く」という選択肢も捨てて、その日の「ホールデビュー」を逃したのだった。
しかし、俺は俺でちょっと大人の階段を登った気になっておったが、彼らは彼らでパチンコを始めたんだな……と、何となく羨ましいような、おっかないような、変な気分になった。
4月。高校最後の年だ。6月生まれの俺は18歳の誕生日にビタで免許を取ってマイカーをゲットするため、新年度早々自動車学校通いを始めた。その頃になるともう私生活が楽しすぎて学校に行くのがすこぶるバカバカしくなり、出席日数ギリギリを計算して卒業に過不足ないビタの単位しか狙わなくなっていた。周りの連中も結構そんな感じだったので、当時の高校生ってみんなそうだったんじゃないかなと思う。
で、ある時だ。家の近所でNと会った。Nは幼馴染ということもあり、元・親友たちと疎遠になってからも普通に遊んでいた。学校にあまり行かなくなり世相とズレて来てる俺に、彼のくれる最新情報は大変貴重なソースになっていた。その日も道端でばったり出くわしたついでに缶コーヒーを飲みながらダベっていたら、彼の口から衝撃の事実が飛び出した。
「Eが学校辞めたよ」
「うへぇ……この時期に? なんでまた──」
Eというのはかのグループでリーダー的な存在だった男だった。リーダーもクソもタメ年だったんだけども、ギャグセンスが飛び抜けた明るい奴だったので、いつもメンツの中心にいた人物だった。
「いやー……色々あってさ」
Nくんが語るに、彼はパチンコに激ハマりし、ある時「大工の源さん」(大ブームだった)で11万ほど勝ったのを機にパチプロを目指し不登校に陥ったそうな。それ自体は別に大したことじゃないのだけど、そこで彼は(Nくんが言うところの)「良くない人ら」との人脈を作ってしまい、自転車窃盗などを行い始めた。自転車窃盗は日常的に遊びの延長として行われており、彼が補導された時には余罪が大量にあったとの事。彼はそれで学校を謹慎になるが、謹慎中にゲーセンにてもうひとつ事件を起こしたらしい。
「何があったの?」
「バーチャで負けて、灰皿投げたんだよアイツ」
「……誰に?」
「何か、たまにいる、アキラ使いいるじゃん?」
「あー、あれ田中くんのツレの人だろ?」
「そう。まじでアイツ……」
「バッカじゃねぇの」
灰皿投げ。これチキンな相手と戦って負けた時にカッとなって良く行われていた行為だった。いわゆるアストロシティ筐体は背合わせになっていて、対戦相手の顔は見えないようになっている。筐体の向こう側の相手にとってみればいきなり頭上から灰皿が落ちてくるようなものなので結構びっくりするのだ。ただそれは勝手知ったる身内相手であり、知らん相手にやると完全にトラブる。しかも彼がその時灰皿を投げた相手は地元でめちゃくちゃ有名なヤンキー(気に入らない奴の耳たぶをちぎることで知られていた)の先輩にあたる人であり、見た目もすげー怖いし誰もがあんまし近寄らないようにしてた人だった。
Eくんはそこが普段から根を張ってるゲーセンであった事と、そして謹慎を喰らってむしゃくしゃしていたこともあり、相手をよく確認せずに投げたんだろう。そしてその灰皿は美しい放物線を描き、怖い人の頭に見事、スコンとヒットしたそうな。
「もうボッコボコだったよ。便所まで引っ張って行かれてさ。5分くらいずっと土下座させられてたぜ」
「うわぁ……。大丈夫だったん、アイツ」
「いや、そっから俺も会ってないんだけど、謹慎中に退学して、今連絡つかないんだよね」
「ゲーセンは? 警察とか来た?」
「いや、通報しなかったって。Eは出禁になったね」
「あれま……迂闊な奴だなぁ……」
余談だけど後年、俺はその「怖い先輩」と仲良くなる機会があった。話してみるとちょっとバカだけど風俗の呼び込みやってる普通の兄ちゃんで、想像よりもかなりフレンドリーな人であった。酒のんだタイミングでEの灰皿事件のことを聞いたら、彼は「覚えてない」との事だった。彼にとってはその程度のことだったのである。が、Eの心はそれでどうやら折れてしまったらしい。
「なるほどなぁ……。大変だなお前らも……」
「うん……。みんな感じ悪いんだよ最近。万引ばっかしやがって……」
そう。俺が彼らと袂を分ったのは、流行の兆しがあった「万引」が超ダサかったからでもある。率先してやってたのはEと、そして高校から仲良くなった奴らだった。NもKも(もちろん俺も)万引は一切やっておらず。ちょっと付き合いきれない部分があったのは確かだ。もしかしたら、Kと彼女に纏わる「こころ」事件が無かったとしても、俺は早晩彼らから離れていたのかも知れない。というのは、自分の善意に信頼を置きすぎか。
「お前もバカみたいな事やってねぇで、こっちこいよ……」
「あー、お前楽しそうでいいなぁ……」
うん。と答えた。飲みかけの缶コーヒーを喉の奥に流し込んで、もう一度頷く。
「楽しいよ、毎日」
そこから5年ほど経ったある日。5歳上の彼女と別れてしばらく経った頃だ。Eを見かけた。実はその頃になると俺は元・親友たちのほぼ全員──なんならKとすら和解しており、また普通に遊ぶようになっていた。ただEだけは退学以降素性が知れず、どうなっていたのかもわかっていなかったのである。彼を見かけたのはパチンコホールだ。初代の「北斗の拳」を打ってたら、隣にいたのが彼だった。俺は一発で気づいたけど、彼がこっちに気づいていたかどうかは分からない。
無表情でレバーを叩いて、中押し。メダルを入れては飲まれ。飲まれては出し。そうして彼は、極めてつまらなそうに箱を持って、ジェットカウンターの方へと、少し揺れながら消えていった。
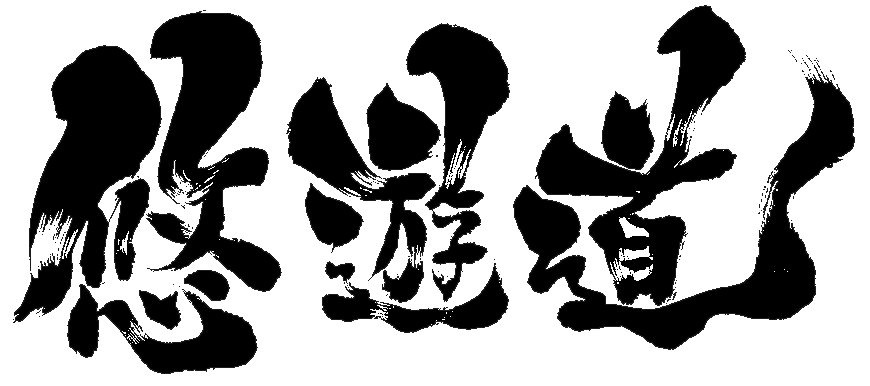


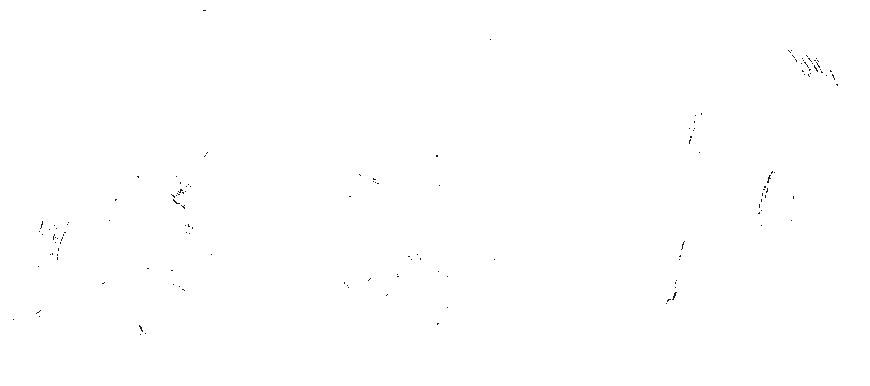
色々な者がありますね
自分も過去には結構そういう経験もありきです
パチプロ目指して 学校辞める当時ではありえる話
けど現在どうなんだか 兼業してようやくといったところですか
厳しい時代になりました・・
さて今年一年の締めお疲れ様でしたそして来年もどうぞよろしくお願いします
ツルッツルだよさん。
チワッス! こちらこそ、ありがとうございました。良いお年をお過ごしください。
また来年よろしくおねがいします!!
悪い方へ行く人、居ますよね・・・
大学の先輩が窃盗で捕まって新聞に名前が出てるの見て「あぁ大人になったんだな」と謎の大人感を感じたことを思い出しました。
白いシローさん。
チワッス! 何かアウトロー感とただの悪人を勘違いしてるみたいな感じしますよね。特に万引は最高にダサい。