今回のテーマはトラブル。自分は打ち手としてはかなりの穏健派なのだけど、この歳までやってますからね。それなりにありますよ。
とはいえ、1本丸々コラムにするほどのネタは思いつかないや。覚えている物を列記する形でいきましょう。
☆一番ムカついたのは…
これは以前書いていたパチンコ機種回顧録のモンスターハウス編で記事にしたっけ。玉泥棒事件の時のことです。
この時は離席中にドル箱の山を盗まれましたね。盗っ人にも腹を立てたけど、追い打ちをかけるがの如くな店員の言葉にキレた。
盗難の報告をすると
「出玉の管理はお客様の責任ですので」
そりゃそうだ。警察を呼んでくれると思ったけど、面倒なんだろうと納得して
「はいはい、とっとと帰りますよ」
と一言嫌みを返すと、
「いえ、この後もご遊技なさるかはご自由に」
ってさぁ、また盗まれても何もしてくれない店で、誰が打つかっての。当然、そのホールは何年も前に潰れました。
☆なんで俺の台でお前が打ってんだよ事件
去年だったかな、攻略で名を馳せたミネッチ君(ヒラ打ちも凄い)が、「離席して戻ると、知らないオッサンが自分の台で打ってたことがある」と話してくれた。当然そのオッサンはミネッチの持ち玉で遊技中だったそう。
「それ、僕が打ってる台ですけど」と言うと、オッサンは「そうか」とだけ言って去っていったらしい。これって絶対確信犯だよね。
何も言えない人だったら、それこそ出玉を交換(窃盗)してたろう。
しかし、ミネッチも人がいいよね。実は自分も駆け出しの頃に羽根モノで同じことがあって、その時は後ろから椅子(今のホールと違い、固定式ではなかった)を蹴りあげて、「何やってんだゴラァ!」とやったもん。
犯人のオヤジは「悪い、悪い」と笑って逃げてったけど、当時まだ痩せていた自分はそんなに弱々しく見えたのだろうか…(笑)。
☆ゴト師事件(犯人は見ていないけど)
これもジグマ時代の話。小さい店だったから、スタッフもみんな顔見知り。負けて帰る日は「スカジャンの背中の虎が、今日はネコに見えるね」なんて軽口を叩かれる程度には雑談できる仲だったなあ。
そんなホールである日、店員さん数人がダッシュして、のどかな店内に緊張が走ったことがあるんだよ。
後で話を聞くと、どうやらゴト師の捕り物だったらしい。結局、逃げられたようだけど、最初からメドをつけていたとのことで、「それなら俺にも教えてくれれば、いいネタができたのに」なんて思ったよ。まあ、ただのお客さんの自分に言うわけないけどね。
ゴト師といえば、ある日常連のオバサンに「安田君、今日ゴト師が来てたのよ。なんか台に突っ込んでてね」とか相談されたっけ。セル使いか?
いやいや、自分はただの打ち手ですから。名作漫画「銀玉マサやん」なら一肌脱ぐところでも、「うん、それは店員さんに言った方がいいね」としか言えんわな。君子危うき日かよらず。
☆客同士のケンカ
これは口ゲンカは良く見るものの、殴り合いは見ないっすね。
自分は…。ほぼ無いです。いくつかはあっても、武勇伝みたいな格好よいもんじゃなく、いい歳をして恥ずかしい話になっちゃうから言いたくない(笑)。
☆出禁関係
これもトラブルの内に入るのかな。「アンタは出禁だ!」という100%の形はないけど、自分もキャリアが長いから、お断り(「その打ち方はご遠慮ください」等)はそれなりにある。
・もう10年以上前に「ステージ止めしてますよね。やめてください」の店は、同地区のベテラン誌上プロ氏が去年だかに保3止めを咎められた某チェーン。
にたような話は枚挙にいとまなしですよ。
・また、あるチェーンでは割と近年に
「ひねり打ちは他のお客さんから苦情が来たのでやめてください」といわれ、素直にやらないでいると、
「止め打ちも同じく苦情が…」と言われ、
「えっ、すごい俺にだけ粘着する客がいるなあ。連れて来てよ。話をするから」と応じてみた。
でも、これには店員さんは口ごもるばかり。
「もしかして、苦情ってアンタの所の店長じゃないの?(ニヤニヤ)」と言うと、答えられない。
あげくには、「回り過ぎでスタート異常が出ていますので」って、どんどん理由が変わってくじゃん(笑)。
建前はもちろん大事だ。スジが通らない商売は追いはぎと一緒になってしまうから。でもね、その為に平気で嘘をつくのはどうかと思う。しかも、架空の客をダシにしてのでっち上げは、自分のところが責任を負いたくないだけで卑怯じゃね。
たとえ、「ツラが気にいらねえんだよ」を理由にされても、それは一旦受け入れましょう。許せない場合は「じゃあ、出るとこ出ましょう」ってだけだ。
パチンコで勝つなら、日陰者として分をわきまえるべきなのはわかってる。「文句を言われるのは打ち手として未熟だから」との指摘も甘んじて受けよう。
でも、「黙ってお金だけ置いていくのがパチンコ」という流れが進んでいるのは、長くパチンコというジャンルを見てきた者として悲しいことです。
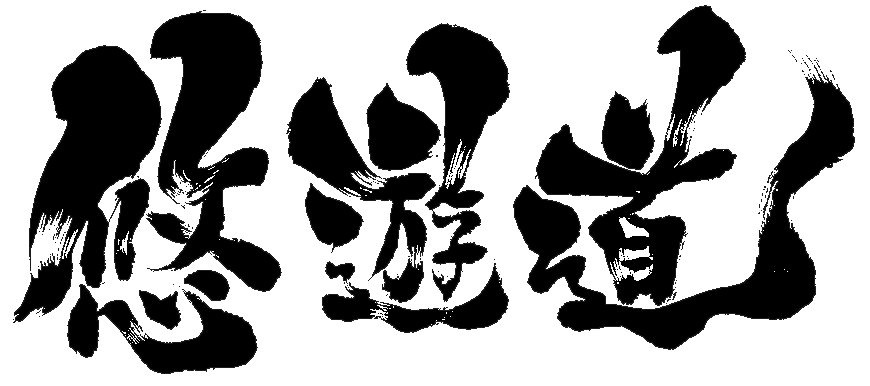


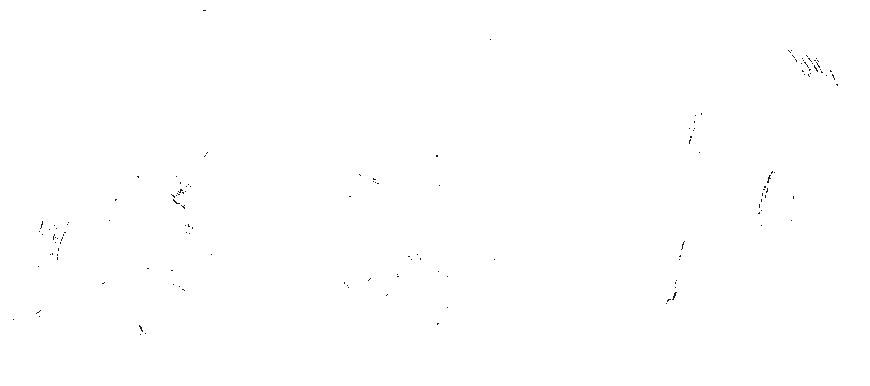
お久しぶりです
トラブル関係は 今のところ さすがにないですが
過去自分途端に思い出したことが・・・・
そう、タンポポのゲームセンターになる前の話です
出禁店舗ですwwww
機種名は忘れましたが当時釘が甘い台があり他入賞口のみ単発打ちで増やしていたら
・・・・ ってことがありました
唯一の思い出でもあります
私が記憶している中で最も変わったのは、堂々と「千円くれ」と言ってくるおっさんでしたね。ドル箱タワーで気分良くなっている客ばかり回っているので、それなりに成果は得ていたようです。私も千円二千円寄付したような、、そのくらい余裕で勝てている時代でしたね。
僕も一度でいいからホルコンで分かるくらい他者と違う回転数や出玉量を出してみたいなあ(笑)回転寿司は好きですが…
長年打ってると自他共にトラブルはありますよね…今は固定ハンドルSNS=大炎上の時代。ミネッチさんの入禁出玉没収の話題じゃないけどトラブルに立ち向かうのは無理で、波風立てずにやり過ごすしかない。ガチプロも演者さんも大変な時代…何しろホールにゆとりがないから、稼ぐ奴は要らないって話に
出玉管理も出来ない店は嫌だな…客減りが酷くて台パンする客に注意しなくなったりしてる店もあります。そんな客を排除しないからも含めての客離れだけど、追い込まれたらそのあたりの判断が出来なくなるんでしょうね。
固定ハンドルで、ぶん殴られてるの見たなぁ。
私はパンチパーマ店員さんには、好かれてました。
フィーバーゴールドとかの出目表とか、発見されて
引きずり出された人もいたなあ。なつかしいわ。
安田プロが数人に囲まれた話はDOKさんと3人談義の時にうかがいました♪(笑)
まぁパンチ店員のいる昭和の時代は、客層も今とは全く違いましたよね?
私が通っていた店でも、40前後のガラの悪いオッサンが出ないのに腹を立ててドル箱を投げて、もの凄い音が店内に響き渡り・・・「うわっ!こりゃ店員にドつかれるわ(汗)」って見ていたら、そのお客をなだめるように店の外へ・・・
何でも地元の893だったそうです(汗)
よくまぁ、こんな時代にプロ張ってたもんだと感心します(笑)
玉泥棒に関しては、何もやってくれないですね。
なので、途中交換ができる店なら、あまりに積んだときは交換するのが無難でしょうね。等価交換ならなおさら。自分なら別積み要求されたらそれは交換しちゃいます。自分の目の届かないところに財産を置いておくのは生理的に無理だから。最近は、非等価ても当日の再プレイは交換分全部のところがかなりあるので、それを活用するのがベストかと思います。
ツルッツルだよさんへ
うわっ、それはみんな知っててもやらない行為ですね(-_-;)
若気の至りということで、悔いとともにわすれないわけですね。
わかります。
獣さんへ
潔すぎて笑えますなあ(-_-;)
でも、私も寸借詐欺系の「競馬でやられちゃって、電車賃貸してくれないか」とか、ストレートに「お金貸してください」と言われたことがあったり…。
しゃだいさんへ
店が強くなり過ぎたのは、打ち手側の抵抗が弱かったせいでもありますが、「もし裁判で負けたら、客全員に責任が取れない」というのもあるかも。
お客さんが減って、タチの悪い打ち手がのさばるの図式は昔から繰り返されてますなあ。
蕨さんへ
殴っちゃダメですよね(笑)。
実は私、ニューパニックという機種でイヤホンを咎められ、「退場!」と元気に宣告された経験があります。
後に回転中の音でタイミングを取って、もう一度行きましたが、その時は常連さんか゜かばってくれて「一日当りを10回まで」という条件でやらせてもらえましたが。
パチドランカーKさんへ
いやいや、ジグマってた店で反社の人を見たのは一人だけです。
あの時はいつも店で一番威張ってる人が「玉を持って行って返してくれないんだよ」とへこんでいたのが印象的でした。
ニュートクオさんへ
そうそう、別積みされると、トイレに行くたびに確認しちゃいますね(-_-;)
そういうのを考慮すると、パーソナルシステムはやっぱり良いですね。
スマパチも同じくですが、カードの抜き忘れが怖いですけど。
随分昔、駐車場から花火大会の打ち上げ花火がキレイに見えるホールへ朝から浴衣で男女4人ツレ打ち。
花の慶次斬、私だけ朝から軽快に城門突破しまくり。
当たるとバラバラに座ってるツレが声を掛けに来てくれる。
「すごぉーい!夜は奢ってもらわなくちゃだねーw」
「おー任せとけ!早くそっちも当てなよw」
10連くらいで終わった後、100回転ちょいでまた当たり。連チャンも続く。
「すごぉーい!すごぉーい!」
「今日はモロタな!ハッハー!」
気分はもう加賀百万石、金のキセルの前田の殿様。
都合二十数回当たりで1箱のまれてドル箱上げようと手を伸ばすと「ドル箱少なすぎない!?」
ハマりまくってるツレ3人が、オレの持ち玉で打っていやがったw
おめでとー!と言いに来てたわけではなく、店員が降ろしたドル箱を取りに来てただけだったw
そいえば店員が「浴衣のお客様3名様は、お客様のお連れ様で間違いないでしょうか?」なんて聞いてきたな……。
出玉を盗まれたのは、この時が最初でした(これが最後であってくれ)w