筆者は基本的に隣に人が座ってる状態でぱちんこを打つのが好かん。知り合いとかなら良いのだけども、知らん人がいるとどうにも集中できんのだ。
例えば以前紹介した人々もそうだけども、一旦集中が乱れると台に向き合うというよりも、隣人の挙動が気になってそっちの観察ばっかりになってしまう。
例えば、5年前に実家近くのパチ屋で遭遇したあの人もそうだった。
大往生おばあちゃん。
筆者、産土(うぶすな)は世田谷だが育ちは長崎県の佐世保市という街である。なんでそうなったかというと単純に親父とお袋が離婚したからだ。通常そういう場合は母親に親権が行きそうなものだけどもウチの場合は親父が筆者を引き取ったので、離婚の理由もまあそれなりにお察しという所だろう。したがって筆者には「育ての母」というべき存在が別にいるのだけども、それが父方の母──つまりは祖母であった。
おばあちゃんは大変に素敵な人であった。
父親も母親もどっちかというとイカれ寄りの人間なので子育てなんぞ土台からして無理そうな感じだったのが、この祖母のおかげで筆者はギリギリでドロップアウトせずに大人になれたと言っても良い、恩人中の恩人である。実際、筆者は彼女のことが大好きであったし、小学校に上がるくらいまでは袖口を引っ張って『グラディウス』でいう所のオプションの如くどこへでもついてまわるような、生粋の、おばあちゃんっ子であったのである。
そんな祖母であるが、十数年前に痴呆を患ってしまった。
最初は「最近の婆ちゃんは物忘れが激しいな」くらいの感じであんまり気にしてなかったけども、さんざん得意でそれまでに2万枚は揚げたであろうコロッケの作り方が分からなくなってしまった辺りで「あ、ボケとる」と気づいた。当時はすでに家から出てしまっている時期で密に過ごす時間が激減していたのもあるけど筆者が気づいた時には症状もいよいよ進行しており、日常生活にも支障が出てた頃合いだった。が、もちろんその祖母と一緒に暮らしてた父親はそんなのとっくの昔にご存知だったらしく、その上で、親戚の力を借りながら自宅での介護を継続する方針を固めていたそうな。
終末のシーンを自宅で。家族に看取られながら。
これはいわゆる「大往生」というやつだろうけど、実際そうやって有終の美を飾れる年寄というのは全体の中でマイノリティであるそうな。大抵は病室で。あるいは老人ホームで。または、最近だと誰にも看取られず孤独に。恐怖に打ち震へながら死んでいく。そう考えると、お婆ちゃんの最期はきっとマシなものになるんじゃないだろうか。とか思ってたら、彼女は82歳の誕生日直前に階段で足を踏み外して骨折してしまった。季節外れの大雪が佐世保の街を襲った日である。自宅前の、石段だった。
年寄にとっての「骨折」は、姉歯一級建築士設計の高層ビルに近い。その心は。どちらも二度とたてないでしょう、だ。ご多分に漏れず、お婆ちゃんも車椅子生活になり、その生活難度は著しく上昇した。当初はそれでも自宅での介護を続けてた親父と親戚の努力には心からの敬意を表したいけど、結局、3年ほどで老人ホーム入りが決まった。佐世保の町外れ。川沿いの建物だった。
その頃、筆者は浅草に越してきたばかりだった。毎日拙いながらも物書きをしたり出張したりとそれなりに頑張っていた時期で、そんな息子に余計な心配をかけまいとしたのか、親父も親戚もおばあちゃんがどういう状況なのかは一切教えてくれず。ただ「元気にしとるよ」とだけ定期連絡を入れてくるという、何のための近況報告なのかよく分からんが、とにかく筆者も筆者で「ああよかった」と毎回なんとなく安心する感じの、今思えば、ふんわりとした相互理解の上で問題を棚上げしてた気がする。
齢百に近い婆様が骨折して元気にしとるわけがないのだけども、なんとなく、あの袖を引っ張ってついて回ってた幼き頃に感じた、おばあちゃんの偉大さや、強靭さ。そして矍鑠とした元気な姿が先に立って、死や衰や病や老というものが、彼女の周りだけは避けて通ってくれるのではないかという鷹揚な期待が、ほんとにのんきに、筆者の脳を麻痺させていたのだと思う。なんなら、お婆ちゃんは永劫に生き続けるんじゃなかろうかと、そんな馬鹿な予感までしていた。
今夜が峠だといきなり知らされたのは5年ほど前のことだ。親戚から電話があって、慌てて職場に連絡し、群馬行きの出張をキャンセルしてもらった。すぐにスマホを使って長崎空港行きのチケットを取って電車に飛び乗り、随分久しぶりに帰郷した。いよいよ危ないと聞かされていたけど、婆ちゃんは点滴一発で復活しており、ベッド脇に座って、親戚一同が集まる前でケロっとお茶を飲んでいた。
「ほら、ひろしが来たよ」
親父が言う。婆ちゃんはふわりとした笑みを浮かべて小首をかしげた。ボケは美しい。とかいう本を読んだことがある。おためごかしだと思う。実際に介護して回る側は大変な労力を使うし、もちろん経済的な負担も甚大だ。現場の方々からすると唾棄すべき綺麗事なのはわかってるけども、わかった上で、それも暴論だと承知で言うなら、もし面倒事から、あるいは人生に於いての些事、付属品から忘却していくとすれば、ボケは本当に美しいのかもしれない。と思った。筆者にとっては人生の大部分を一緒に過ごした、第二の母でありそして人生の師である尊敬すべき女性だけども、彼女にとっては、筆者は人生のある一時期一緒にいただけの、我が子の子。それだけの存在なのかもしれない。なんせその時祖母が見せた、ふわりとした、幸せに満ちた、心配事のかけらもない、いわゆるアルカイック・スマイルは、筆者が今までに見たこともないほどあどけなくて、そして筆者自身もまた余計なものとして綺麗サッパリ忘れ去られてるのだという事を、秒で察することができる類のものだったからだ。
介護士さんに恵まれたのか。あるいは総ての介護士さんがそうなのか。後者であれば最高なのだけど、兎に角、なんとお婆ちゃんはその時点で「ずっと旅館に泊まっている」と思い込んでいた。菩薩のような笑みを浮かべ、か細い声で「ここの旅館はサービスがいい。料理も美味しいよ」と褒めちぎる。彼女はそういう人だった。
お婆ちゃんはその3日後に亡くなった。
一度東京に戻ったタイミングで即座に呼び戻された筆者は、ギリギリで死に目に会うことが出来なかった。せめてもの餞に、通夜はずっと線香の番をした。葬式では、親父が気を利かせて親族代表のスピーチを任せてくれたので、筆者はしっかりとその役割を果たした。
「いままで迷惑ばっかりかけてごめん。お婆ちゃんは、ぼくにとってのお母さんでした」
葬式が終わり、火葬場まで向かう。親戚のおっちゃんが操るバンに乗って、一時間ほどのドライブだった。車内はカラっとしたもんだった。病気で死んだわけでもないし、老衰で、嫌なことを全部現し世に置いて逝った婆様。それはとても幸せな最期だし、さらに一度奇跡の復活演出を経た事もあり、全員覚悟完了していたのも大きい。兎に角、こういっちゃなんだけども、和気あいあいとした雰囲気だった。婆ちゃんの失敗話や、恥ずかしい思い出。親戚たちが語るそれらを聞きながら、助手席の窓を全開にしてタバコを吸う。
火葬場に運ばれた婆様の遺体がウェルダンに焼き上がるまで、我々親族一同は控室みたいな所で弁当を食って過ごした。田舎特有の風習かもしれんが、みんな大量の菓子を持ち込んでいて、親戚の下の子──筆者にとっては従姪が、ダイソンの掃除機みたいな勢いでそれらを食っていた。筆者はめったに会わない同年代の旦那衆と喫煙所で缶ビールを飲みながら過ごした。本家の長男ということで筆者のヒエラルキーは一番上であった。とは言え、物理的な距離は筆者が最も遠い。したがって、扱いは客人(まろうど)である。どことなく寂しい気はしたけど、これはこれで気楽だ。気楽ついでに酩酊寸前まで飲んでやった。
やがて焼き場からの連絡があり、我々はお骨を拾うための四畳半ほどの部屋に入った。鉄製のグリル機みたいなのが壁から引き出される。びっくりするほど小柄な人物の形で、骨が気をつけの姿勢で並んでいた。
「あら! お母さんちっちゃくなったねぇ!」
親戚の誰かが言う。思わず皆笑う。火葬場の職員の人も苦笑しながら、みんなで一緒に骨を拾った。
「ほら、ここ。ここが折れてた所さ。ネジのハマっとるもん。このネジでボケたったいお母さん」
「いや、お母さんネジつける前からボケとらしたよ」
「係員さん、このネジも骨壷にいれた方がヨカと?」
「いえ、それは入れなくて大丈夫です」
談笑しながら作業を終える。100歳の老女の骨は、全部集めても握りこぶし2つ分くらいだった。親戚に泣きながら看取られて、笑顔で骨を拾われる。なんとも清々しい最期だなと思った。
せめて20スロであってくれ。
「ひろし、家まで送ろうか?」
「いや、俺はいいや。タクシー使うよ」
「なんで」
「ちょっと一人になりたい」
「そうね……。喪服のまんまじゃあれやけん。上着持って帰ってやろうか?」
「ああ、そうだね。お願いしようかな」
葬式帰りに、筆者はパチスロを打ちに行くことにした。家に帰っても夜まで特にやることがなかったからだ。四ヶ町と呼ばれる、佐世保で一番の歓楽街の外れにはビッグアップルがある。もともとはケイズという名前だったと思うけども、田舎を離れてる間に屋号を変えたらしい。思えば通夜である昨日からずっと缶詰だったので、そろそろ息抜きがしたかったのもあるし、それより、なんとなく人生の節目として、パチスロを打ちたい気分だったのだ。何も考えず、ただレバーとボタンを叩いて。虚無の心境で、頭の中をからっぽに。あの贅沢で、それでいて空虚な時間に身を委ねたい気分になったのだ。
車を降りて、深呼吸して少し散歩する。ようやく見つけたスタンド灰皿のあるタバコ屋で缶コーヒーを飲みつつ二本ほどタバコを吸って、そうしてたっぷり間をおいてホールに入った。紫の煙。金属音。ワックスと芳香剤の香り。肩を並べて座る人々と台が醸し出す鉄火場の雰囲気を胸いっぱいに吸いながら、エスカレーターに乗って二階へと向かった。財布の中身を確認する。連チャンで航空チケットを買ったので軍資金が心もとない。舌打ちして、仕方なく5スロコーナーに向かう。
何を打ったのか覚えていない。ただ、一人になりたくて閑散としたバラエティコーナーの端っこに陣取った。メダルを借りる。投入する。レバーを叩く。ボタンを押す。何度か繰り返す。空虚で贅沢な時間だった。
5分ほどして、隣に誰かが座ってきた。舌打ちしそうになる。なんせ筆者は、誰かの隣で打つのが嫌いだし、その時は特に、一人で静かに打ちたかったからだ。どんな野郎が座ってきたのかと思って横を向く。ああ、と思った。最悪だ。
「あ。どうも──」
「ああ。さっきは──」
お互いに会釈する。ついさっきまで一緒に並んで骨を拾っていた親戚のおっちゃんだった。喪服のまま、パチ屋に直行してやがる。向こうも同じ事を思ったのだろうことが、その目の奥の色でわかった。互いに何も言わず、台に向き合う。メダルを入れる。レバーを叩く。ボタンを押す。押す。押す──。
メダルよメダル、一刻も早く無くなれ……。
パチスロを打ち始めて22年くらいになるけども。この時ほど居心地の悪い隣人というのを筆者は他に知らないし、恐らく超える隣人は出てこないと思う。
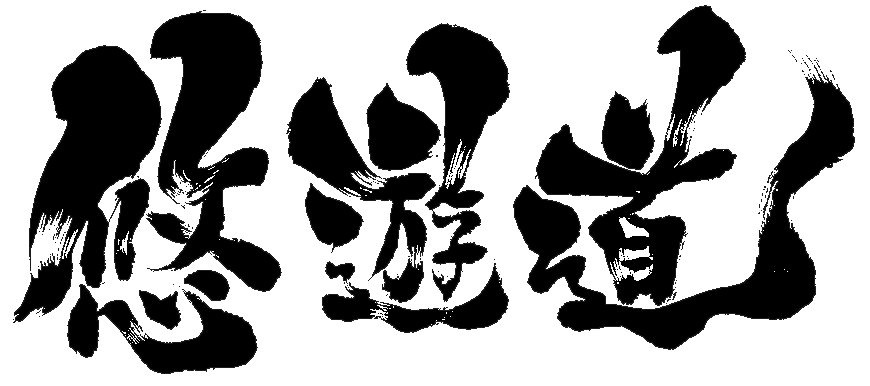


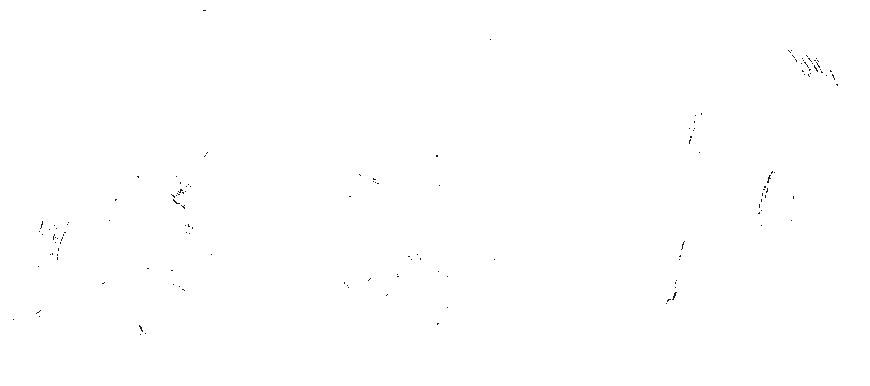
あしのさん、あけおめ!
隣人伝説のテイストが素敵な話モードになっとる…
生きていれば少なからず何人かは今の自分を形成するのに切っても切れない存在の知人はいますよね。また、長く打ってきたパチ・スロなので色んな人生イベントに絡む思い出の遊戯日なんかもあったりして。そして、猛烈に一人で無心にリールを廻しストップボタンを押していたい場面もありますよね😉
駄目旦那の典型ですが秋田に里帰り出産を迎える嫁、義理の母から「今晩か明日朝かな?」と電話があった後何故か落ち着かずにホールに向かっていた自分が…バラエティーコーナーの火曜サスペンス劇場と戯れておりましたよん💦
おばあちゃんの事が大好きなんですね
自分も隣に人が居る状態で打つのは非常に苦手ですがそのシチュエーションは経験した事無いですね
色んな事思ったり考えたりした後の無心になる時間と言うかなんというかタイミングの悪過ぎる来訪者というか…年越しを邪魔された感と言うか誰が悪い訳でも無いのに自分なら非常にモヤモヤしたと思います
検討外れだったらごめんなさい
さてはオメー、隣人伝説を108つ語るハラだろ?
オメーが1つ語る度におれは自宅の明かり(ローソク)を1つ消している
全ての明かりが消えたとき、おれの命の灯も消えるだろう…
「心配すんなよ旦那、読者いねえと寂しいもんな、いいよ、最後までロムってやるよ、邪狩の旦那」(佐倉杏子節)
上でしっかり仕事こなしたので、当コメは非掲載でお願いします(担当BBAの権限により掲載します。すまんの)
今回の記事は世辞抜きで心に届いた
笑いと感動が込められた傑作だったがキモさが足りない
もっと精進しろ、乙
レギュラーマンさん>
チワッス! 落ち着かずにホール。すっげーわかります。何か人生を左右する状況にある時、とりあえずホールに逃げてる気がします自分。毎回のごとく。ちなみにこれも広義の依存らしいです。あわわ。
夾竹さん>
チワッス! そうなんですよ。なんか「ひとりになりたくていくパチンコ」というのも確実にあるんですよね。自分が惹かれる魅力の一つとして。まあ公共の場なんで完全にひとりというのは無理ではあるんですけども、どうしても「今は隣やめてくれ」というタイミングがどうしてもある感じです。ばあちゃんはホント大好きでした。ザオリクがあれば……。
田中さん>
チワッス! うは。まっきゃんのファインプレー(?)が発動してますね。ありがとうございます! ちなみにロウソクと命といえば、ファミコンの源平討魔伝を思い出します。なんかライフゲージがロウソクで、消えたら死ぬ感じのシステムでした。怪談でロウソクを消すのもそうですし、命とロウソクの関連も調べると面白いかもしれませんね。次の衒学ネタに……(笑)